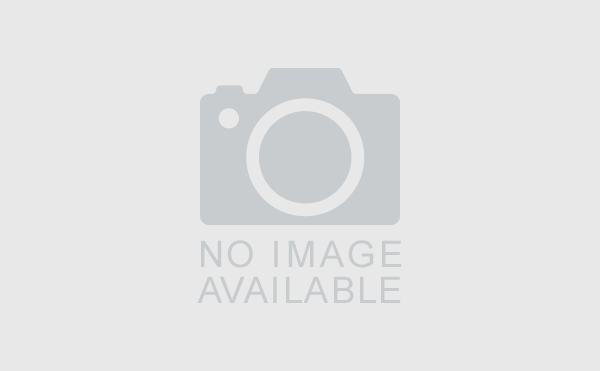勉強とテレビゲームが似ている理由
親子塾えすてぃむの子の教科学習のスタイルを見ていると、大きく2パターンに分かれていることがわかります。
その2パターンとは、「学問として、教科学習を楽しむパターン」と「ゲームとして、教科学習を楽しむパターン」です。
「学問として、教科学習を楽しむパターン」を持っている子は、「なぜこの現象が起こるんだろう?」「これってどういうことなんだろう?」という問いが、教科の内容でも頻繁に起こります。
だから、自然とじぶんで本を読んだり、インターネットで情報を集めたりして、勝手に学びを深めていくんですね。
「ゲームとして、教科学習を楽しむパターン」を持っている子は、はじめは「勉強は嫌い」というところに立っていることが多いです。そして、テレビゲームは大好き。
でも、実は、テレビゲームと教科の勉強には似ているところが多いんですね。
ぼく自身がテレビゲームが大好きなので、似ている点が浮き彫りになりました。
では、テレビゲームは楽しいと感じるのに、 勉強は楽しくないと感じるのはなぜなのでしょうか?
それは、
「テレビゲームは、”やりたい”からスタートしている」
「勉強は、”やらされる”からスタートしている」
という前提があるためです。
”やりたい”と”やらされる”は、まったく違いますよね。
テレビゲームがやりたくなるのは、「ワクワク」があるから。
「ワクワク」の正体は、人によってさまざまですが、あえて言語化すると、
・可愛い(かっこいい)キャラクターを自分で操作できる没入感
・プレイするたびにうまくなる成長感
・敵を倒す爽快感
などがあるかと思います。
「没入感」「成長感」「爽快感(達成感)」って、教科学習にも多く含まれているんですね。
国語や英語の文章を読んで、その中に入り込む「没入感」
社会の用語を覚えて、それが結びついてきたときの「成長感」
数学の応用問題の解き方が閃いた時の「爽快感」
やっていくとわかりますが、これらはとても似ている感覚なんです。
ところが先ほど言った「前提(”やりたい”か”やらされる”か)」がそもそも違っているため、なぜがうまくいかない。
教科学習が楽しくなって、結果としてテストなどの客観的なデータでも得点力がついていくのは、この「ゲーム感覚」を理解しているかどうかは重要な要素だと思っています。
現在の入試では、読解問題が増えて思考力を試す傾向が強くなったとはいえ、結局は「点取りゲーム」の側面がとても強い。
ということは、ゲーム感覚で勉強をとらえることができると、ちょっと違った景色が見えてくるんですね。
今書いたことは、親子塾えすてぃむのセッションに来ている子たちには、最初は話していません。
えすてぃむに教科学習を見てほしいと思っている子は、来た時点で「勉強ができるようになりたい」という気持ちをすでに持っているためです。
だから、えすてぃむでは、「没入感」「成長感」「爽快感」が得られるように、いっしょに教科学習のセッションを組み立てるのみなんですね。
それは、とても楽しいプロセスですし、その子が欲しい成果を得ています。
教科学習も本当はエキサイティングなものですもんね。